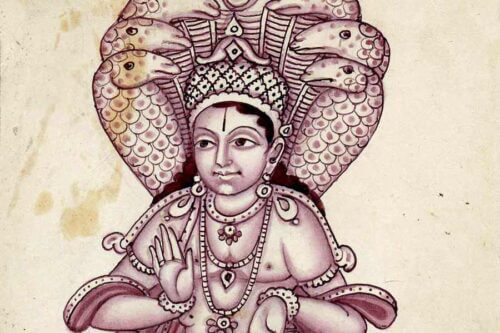〝パーマカルチャー〟 今では、ヨーガ実践者にも耳に入る言葉となっているのではないでしょうか?ヨーガの実践は、アーサナ・プラーナヤーマ・瞑想の他にも、日常生活での倫理的な配慮や生活習慣を最適な状態に保つといった実践があります。 このような日常的な実践は、複雑な人間関係や、環境問題に左右されやすく、都市生活での実践の維持に抵抗を生む場面が多いかと思います。 今回、パーマカルチャーの基本的な講義を聞くことで、倫理的な配慮とは?または、最適な生活環境や生活習慣とは…?このような疑問に対して、パーマカルチャーの知識や知恵をヒントに参加者の生活習慣や日常の態度を向上させることが目的となります。 もちろん、ヨーガ実践者以外の方にも為になる講座ですので、一般の方、またはパーマカルチャーに興味を持っている方の参加も可能です。 【日時】2017.3/25 17:30~20:00 【場所】東京ヨーガセンター 【料金】3000円 【定員】25名 【講師】設楽清和(したらきよかず) 1956年生まれ。上智大学外国語学部フランス語学科卒業後フランスグルノーブル大学文学部およびアメリカ合衆国ジョージア大学大学院人類学科に留学して研鑽を積む。一方、特殊法人国際観光振興会に勤務の後、新潟にて農業に従事。現在、神奈川県藤野でパーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事として様々なワークショップを通じ、身の回りのあらゆる動物・植物・建築・エネルギー・コミュニケーションなど多種多様な要素を活かす生活スタイルのデザインを提案し、永続可能な社会の基礎となる人間と自然についての基本理解を深めることをライフワークとしている 【パーマカルチャーとは】 パーマネント(永続性)と農業(アグリカルチャー)、そして文化(カルチャー)を組み合わせた言葉で、永続可能な農業をもとに永続可能な文化、即ち、人と自然が共に豊かになるような関係を築いていくためのデザイン手法です。私たちの命を支えている自然の恵みである食べ物やエネルギー、水などがどこからきてどこへ行くのか、そして自分の毎日の生活がそれらにどのように関わっているのかを知り、より豊かな生命を育むことが出来るようにそれらと関わっていくこと。そして喜びを分かち合うことを前提とした人間社会を築いていくこと。これらを実現していくために自らの生活や地域、社会そして地球を具体的にデザインしていきます。 【講座内容】 いくつかあるパーマカルチャーの原理原則から、循環性・多機能性、・重要機能のバックアップについてのお話をします。特に自分の生活の中で、具体的にどのような工夫ができるのかを様々な事例から学ぶだけではなく、自ら考え、工夫する見方や思考方法についてワークショップ形式で学んでいきます。 ●循環性 生物が最初に作り出した永続へとつながる仕組みは、この循環性だったと考えられます。循環の当然の帰結としての特徴は、ゴミがでないということです。このため、環境に対して負荷をかけることもありません。 単純化して言えば、ゴミ=資源となる仕組み、すなわち、あるシステムから出されるアウトプット(ゴミ)が他のシステムのインプット(資源)となり、それらのシステムが一つの輪になって、どこからもゴミが出ることもなく、また、資源が足りなくなることもないのがこの循環性です。 ●多重性(多機能性) 多くの生物、特に進化した生物は必ず多くの機能を果たすことができる多機能性を備えています。鶏であれば、卵を産むことだけではなく、虫を食べたり、地面を引っ掻いて耕起したり、それに糞を出して土を肥やすこともできます。 このように自然を構成する個々の要素に多くの機能があることで、自然の中には多様な環境が生まれて、より多くの生物が生まれ、生きることができるようになります。 また、このような多く機能を果たすことで生物自体もストレスなく生きることができます。 生物でも無生物でも、一つのものに多くの機能を持たせることで、一つの機能だけしか果たせないものを多く集めるのに比べて空間を大幅に節約することも可能です。パーマカルチャーのデザインでは、そのデザインを構成する要素に少なくとも3つの機能を持たせることを考えます。 ●重要機能のバックアップ これは生きていく上で欠かすことのできないことやものには複数のバックアップを用意するということです。 例えば、水であれば、現代人のほとんどは、水道以外に水源を持ってはいないと思います。しかし、地震などの災害が起き、水道管が破裂するような事態が生じてしまえば、生きるに欠かすことのできない水の供給が断たれて生命の危機に陥ってしまいます。 雨水タンクを設ける、あるいは予め井戸を掘っておくなどしておけば、水道が断水になってもすぐに生命の危機にさらされることはありません。このように食べ物や、水、職業などについても安定した生活を営んでいくには複数のバックアップを持つことが必要と考えられます。 【申込み】東京ヨーガセンター さとうまで sato@tokyoyogacenter.com
BLOG
ブログ