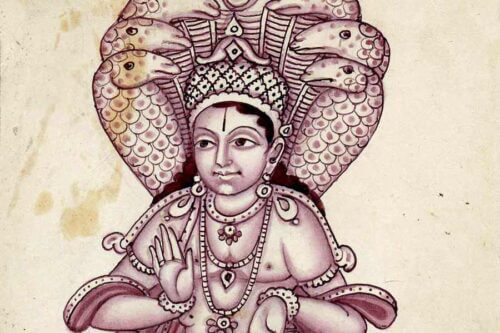音楽と自然の摂理

すなおです。今回は音楽の話でも(笑) 「四季の歌」って知ってますか?
https://bit.ly/2PoepKb あの曲を聴くと、僕は、なんだか暗く、モノ悲しい、憂鬱な、絶望的なメロディーに感じていたんです(笑) でも先日、ピアノ講師をされている知人・Sさんのお話を聞いてハッとしました。
「むかしの日本人は、短調の曲を〝暗い〟と思っていない、そんな感性をもっている気がする」と。 (※短調の曲とは、たとえば「四季の歌」「うれしいひなまつり」「さくらさくら」、外国の曲では「ドナドナ」「トロイカ」など。ちょっと悲しげで暗いメロディに聴こえたりします)
なるほど~!
そう言われてみて、確かに短調のメロディは暗めで悲しげだと思っていたけど、「うれしいひなまつり」「さくらさくら」「四季の歌」などの歌詞を改めて見てみると、別に陰鬱さを表現したいのではなく(笑)、日本の美しい四季の様相を表現したような、すてきな歌詞なんですよね。自分の完全なる偏見、先入観によって、曲の暗い明るいを決めつけていたんだなと、ハッとさせられました。そして音楽だけじゃなく、日常でもこういう決めつけって結構あるんだろうなーと。
さらに興味深かったのは、
Sさんが、ピアノレッスンで小さなこどもに短調の曲を教える際に「これは少し暗めのメロディだね」と言ったら、こどもに「え?なんで?」ポカーンという反応をされた話(Sさんはこどもに余計なことを言ってしまって申し訳なく思ったとのこと)。どうやら、こどもは短調のメロディを〝暗い〟と感じる感性がないようだったのです。 なるほど~!!面白い! こどもはメロディーに〝暗い〟〝明るい〟という先入観/決めつけがなく、音を音そのものとして、純粋に感じ取ることができるのかもしれません。

このエピソードを聴いて、僕はALTANというアイルランドのグループの、ライブへ行ったときのことを思い出しました。 ALTANは〝アイルランド北西部のドニゴールに生きる伝統音楽の精髄を、もっとも美しく、ダイナミックに ヴィヴィッドに伝えるバンド〟と言われています。CDで聴く限り、歌やメロディは美しいのですが、どこか影があり、悲しげで、哀愁のほうを色濃く感じるような印象でした。
(myフェバリットソング2曲をぜひ)
https://bit.ly/3fttZik
https://bit.ly/39rOhoq
そんな印象のまま、2018年にALTANの来日公演を観に行きました。ライブでは、わかりやすい楽しさとか、派手さとか、インパクトは特に感じず、表面的にはCDで聴いたときに抱いたのに近い感触でした。ただボーカル/フィドルの女性・マレードさんの透明感のある歌声や存在感が妙に印象に残りました。 ライブが終わったあとは、大きな感動があったわけじゃなかったのですが、そのあとあとまで、ずっ~~~とライブの余韻が残っていて、それは時間がたつごとに消えていくどころか、心にジワジワと浸透していき、静かな感動に満たされていくような、不思議な感触になっていったのです。

それ以来、かつてALTANの音楽に対して感じていた、暗い、悲しげ、哀愁と感じていた要素がまったく違う印象を持ち始めました。明暗という単純な二極化を超えたとこにある、もっと力強く、壮大で、美しい、純粋な何かを感じるようになりました。
その正体はおそらく〝自然の摂理〟〝自然現象〟であり、それを捉えて音に織り込んでいるのではないかと思うのです。
ALTANを聴いていると、(行ったことはないですが自分の勝手な想像のなかでの)アイルランド北西部のドニゴールの風景のなかに身をおいているような気分にさせられます。

もしかしたら「四季の歌」「さくらさくら」「ひなまつり」なども、そういう類の表現/メロディなのではないかと、ピアノ講師をしているSさんの話を聴いて思いました。
そのように世界に無数にあるだろう〝自然の摂理〟が表現された音楽/創作物/芸術などを、純粋な心で触れることができれば、明るいとか、暗いという評価ではなく、もっと壮大な、美しい、純粋な本質が見えてくるのかもしれないなーと思いました。
もっとその深層部にある壮大な、美しい、純粋な本質が、見えてくることもあるかもしれないなーと思いました。まあ、いろいろなことを重層的に捉えていけると面白いですよね。 すなお